軽井沢風越学園には異年齢のホームがあります。
義務教育学校では、今年度は1−4年生のホームが5つと、5−9年生のホームが5つ(幼稚園はまたあらためて)。
それぞれ25人ずつくらいのコミュニティです。スタッフもまざって複数名で担当し、毎朝45分を共に過ごします。子どもたちは昨年とメンバーが変わらず(4年生は上のホームに移動。下のホームは1年生が入ります)。顔見知りのメンバーだからこその成熟したホームができていくんじゃないかな。今週11日にホームスタート。
ホームの意味と価値
ホームページには以下のように書かれています。
風越学園には異年齢構成の「ホーム」があります。異年齢で過ごすことを通して、自分の視線とは違う世界を見る、憧れる、ケアし合う、真似をすることを試してみながら、新しい世界をともにつくります。安心してあそびや学びに没頭するには、自分の存在が大切にされていると感じられる場が必要です。ホームは「聴きあう」ことと「多様さを認めあう」ことを大切にします。わたしたちは学園の中で複数のコミュニティをつくり、そこで経験できることの価値を信じています。ホームのつくり手は一人ひとりの子ども自身です。異年齢で「自分たちの居心地のよいコミュニティを自分たちでつくる」経験を積み重ねることは、「自分たちの居心地のよい社会を自分たちでつくる」原体験になるはずです。スタッフは、子どもたちに過不足のなく関わりながら、共につくっていきます。スタッフはホームの一員であり、ホームがよりよい居場所になるように責任を持つ存在でもあります。さらに、子どもたちにとって最も身近な大人として、安心できる存在であり、なによりホームのつくり手のロールモデルを目指します。
ことばにするのは簡単ですが、実践するのは本当に難しい。なにしろ今までの(日本の)学校教育ではほとんど実践されていないので、実践知も自分たちでつくりだしていくしかない。
開校以来、ホームの単位を変えたり、時間を変えたり、時には「ホームが必要なのか」という議論が起きたりもしました。ホームの意味と価値を確信できないことが子どもにも伝わっていたのか、ホームに子どもが全然集まらない時期も。
特に開校2年目、3年目は苦難の時期を過ごしました。
一昨年に、中学生から「ホームをよりよくしたい」という声が上がり、ホームをよりよくしたいという意思が生まれ、そこからホームの質感がかわってきたなと思います。
これまでの学級経営のように「先生が経営する」ものではありません。リンク先の記事のように、ともによりよいコミュニティを目指してつくっていくプロセスそのものに価値があるのです。
ホーム、5年の時を経て子どもにとっても大人にとっても大切な場に育ってきています。
今年の春休みのスタッフ研修では、2つのホームのスタッフから実践の共有があり、その豊かな実践に嬉しくなりました。ぼくらは確かに積み重ねてきている。
情景
2016年に学校づくりをしたときに、初期メンバーで「情景」を描きました。こんな学校になるといいなという物語を綴ったのです。その時に描いていたホームはこんな感じ。
鈴の音が聞こえると、外で遊んだり、「探究の学び」に取り組んでいた小学生中学生たちも校舎の中にゆるゆると戻ってくる。2つの異なる学年の子どもたちが混じっているホームグループでのサークルの時間。それぞれのホームグループの部屋に丸く置かれたベンチにあつまって座りはじめる。部屋のデザインはそれぞれ個性的。新年度のはじめに自分たちが居心地いいようにリフォームするところからスタートするからだ。「ここ空いてるよ」「お、ありがとうー」。座る場所は毎日ちょっとずつ変わっている。基本の丸は保ちながら、ベンチを前後左右に移動させ、自分の快適な所を探っていく。いろんな人との関係をゆっくりとつくっていく。今日のファシリテーター役の子の「おはようー。昨日どんな1日だった?」の声で、近くで座っている人とのおしゃべりからスタート。「昨日、本読んでたら寝るの遅くなってさ、今日寝不足…。」「何時まで起きてたの?」「12時…。」「今日なにやるの?」「ああ、朝、算数一気に進めたら、今日は今『探究』で取り組んでる映画作りで、動画撮影やるんだ」「ついに撮影の準備できたのか!」昨日あったこと、今日やりたいことを確認していく。「何かみんなで話したいことある?」のファシリテーターの問いかけに、「僕らのこのホームグループの場所、最近ちょっと使いづらいからリフォームしたいんだけれど」「どんなところが使いづらいって感じるの?」「どんなふうにしたい?」「私たちが作った本棚とか使ってみない?」いろんなアイデアが出て、早速明日から取り組むことに。ホームグループ担当のスタッフからは、今日午後来客がある旨が伝えられた。学校案内は子どもと教職員の協同の仕事。今回はこのホームグループが担当だ。ランチタイムに有志と教職員で打ち合わせをすることになった。サークルの最後は読みきかせの時間。司書教諭のみさきさんお薦めの『夏の庭』もいよいよクライマックスだ。物語の共有の時間が終わると、それぞれ自己主導の学びの時間へと移っていく。
最初の頃は2学年ずつで考えていたんですね。
この時描いた情景のようになったこと、まだ辿り着いていないこと、超えていること。
5年間の試行錯誤を経て、よりよく育ってきたなと感慨深いです。
今年も1−4年生、5−9年生のホームでスタートします。
今年はメンバーチェンジなし。2年間のメンバーだからこその成熟が楽しみです。
自由って?
ホームで、子どもたちはいろんな経験をします。
嬉しい経験も、苦しい経験も。
3月の「わたしアウトプット」((1年間の、わたしのここまでの経験・学びアウトプットする場。ひとり20分程度プレゼンする。保護者や風越の仲間がききにきて、お互いの成長をお祝いしあう場。1年生から9年生全員が行う)で、9年生のKさんはホームでのことをこんなふうに話していました。
「ホームでは、やりたいことの意見が真反対で。
体育館で遊びたい人と、その逆で体育館で遊びたくない子もいて。
読書とか掃除はやりたくない人もいれば、その逆に、掃除をみんなにしてほしいけど体育館
では遊びたくないとか。
そういうわがままな感じ。
私的にはどっちもみんなでやればいいじゃんって思うんだけどそうはいかないらしい。
何回も話し合ったんだけど、解決はしなくて何にも変わんない。
これって自由じゃなくて、ただわがままをこう押し付け合ってるだけだなって思っていて、違和感を感じていた。
風越が大事にしてる自由ってこういう自由じゃないと思っていて。
自由イコールなんでもやっていいなのかなって入学する前は勝手に思ってたんだけど、
ただなんでもやっていい自由は、いい意味としても捉えられるけど、悪く言うとにわがままになると思う。
自分のこうしたいとか、ああしたいをずっと押し付けてたら、意見が合うこともないし、
ただお互いにお互いを攻撃するだけ。うん攻撃するイメージなんだね、そういう自由は。
私なりに思う風越の自由は「新しい自分に出会える場」かな。
自由にできることってすごいたくさんあるな。
例えば、自由に話すのもそうだし、自由に好きなことするとか、自由に繋がるとかがあると思うんだけど。
その自由があると、できることが増えるし、選択肢も増えていくと思うのね。
でも、ずっと自由にそのままやり続けるのは絶対無理だなって思ってて。
それは科学の実験と同じなんじゃないかなって思っていて、みんなが自由に何でも入れてったら、爆発しちゃうじゃん。
自由の使いかたを間違えないようにしたい。
いろんな人と協力しながら
いろんな人の自由をもらって、自分の自由もあげて。
そうすれば、新しい自分とも出会えて、自分のことももっと好きになるし、風越
のことももっと好きになるんじゃないかなって思います。
だから、私が思うかざこしが大事にしている自由はいろんな人からもらった自由で、新しい自分の新しい自由をつくっていくことだと思います。」
うまくいかないこと、悩んでいることの中に大切な気づきと学びがある。そこにじっくり自分たちで向き合える余白があること。大人が先回りして解決しないこと。
大人であるぼくらはそこに覚悟を決めたい。うまくいっていることだけがよい状態ではないということに。
大人であるぼくらはそこに覚悟を決めたい。うまくいっていることだけがよい状態ではないということに。
K さんの「私的にはどっちもみんなでやればいいじゃんって思うんだけどそうはいかないらしい」。「そうはいかないらしい」ということばが、違いをちがいのまま受け取る、曖昧さをそのまま手元に持っておく覚悟のようなものを感じます。苫野さんのいう「自由と自由の相互承認」を、ホームでの経験から、自分なりにことばとして紡ぎ出していて、ぼくはきいていて感動しました。
この実感こそが自由の相互承認の「感度」だなあと。
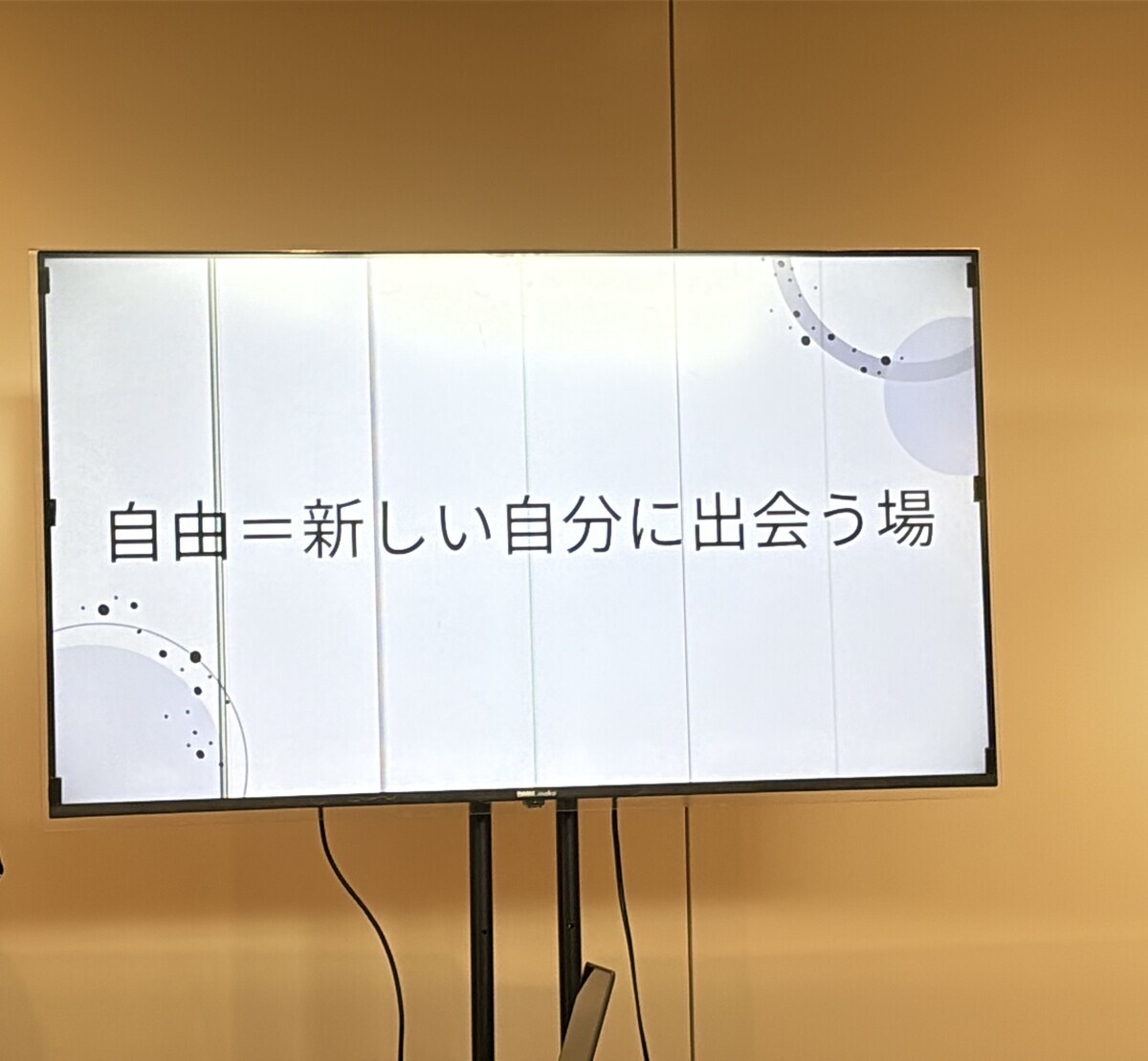
6年目のホーム動き出します。
今年はどんなことが生まれるのか、楽しみ楽しみ。
✴︎校内コミュニケーションシステム「Typhoon 」に時々書いている「毎日うろうろ」より加筆修正して転載。
(関連記事)